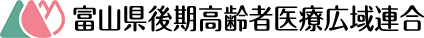よくあるご質問
よくあるご質問
対象者・資格について
1. 後期高齢者医療制度はどのような人が対象者となりますか?
対象となる方は、富山県内にお住まいの75歳以上の方、65歳以上の方で一定の障害について広域連合の認定を受けた方です。
なお、生活保護法による保護を受けている方などは対象となりません。
2. 被用者保険の被保険者が75歳になった場合、被扶養者(75歳未満)の保険はどのようになりますか?
被用者保険の被保険者が75歳になると後期高齢者医療制度の資格を取得し、被用者保険の資格は喪失します。これにともない、被扶養者の方も資格喪失することになるため、市町村の国民健康保険等に加入していただくことになります。
届出(申請)手続きについて
1. 75歳になって、後期高齢者医療制度に加入する場合、何か手続きが必要ですか?
75歳の年齢到達に伴う資格取得については、手続きの必要はありません。資格確認書は誕生日の約一週間前までに郵便でお届けします。
2. 65歳以上で、障害があるため後期高齢者医療制度に加入するためには、申請が必要ですか?
広域連合の認定を受ける必要があります。申請はお住まいの市町村の窓口でお受けします。申請時には国民年金証書(障害基礎年金1~2級)、身体障害者手帳(1~3級及び4級の一部)、療育手帳(A判定)、精神障害者福祉手帳(1~2級)など、障害の程度を確認できる書類等をお持ちください。
なお、75歳になるまでは、この認定を将来に向かって撤回することができます。
3. 転居するときは、何か届出が必要ですか?
1)県外へ転居する場合
お住まいの市町村の窓口で資格喪失の届出が必要です。その際に資格確認書(又は被保険者証)は返還してください。
「負担区分等証明書」(資格や受診時の自己負担割合に関する証明書)をお渡ししますので、転居先の市町村での資格取得の届出時にこの証明書を提出して、新しい資格確認書の交付を受けてください。
2)県内の他の市町村へ転居する場合
お住まいの市町村で住所変更(転出)の届出が必要です。
新しい資格確認書は、後日、郵便でお届けします。
4. 特定疾病に該当しますが、何か届出が必要ですか?
次の特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、お住まいの市町村の窓口で特定疾病療養受療証の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。医療費の自己負担額が、入院、外来別に医療機関ごとに1か月につき1万円までとなります。
①人工透析が必要な慢性腎不全
②血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は第IX因子障害(いわゆる血友病)
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)
資格確認書について
1. 後期高齢者医療制度の資格確認書はいつ頃届きますか?
75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の約一週間前までに郵便でお届けします。
75歳の年齢到達以外の事由で資格取得される方については、お届けまでに数日かかる場合があります。
2. 資格確認書(又は被保険者証)を紛失した場合はどうしたらよいでしょうか?
資格確認書(又は被保険者証)の紛失、汚損、盗難等の場合は、お住まいの市町村の窓口で資格確認書の再交付の申請をしてください。
3. 資格確認書の任意記載事項欄に限度区分や特定疾病区分を記載したい場合はどうしたらよいでしょうか?
お住まいの市町村の窓口で資格確認書交付兼任意記載事項併記申請をしてください。
受診時の自己負担割合について
1. 病院で治療を受けたとき、窓口での一部負担金はどうなりますか?
病院等の窓口で支払う一部負担金は、前年中の所得等により1割、2割又は3割の負担になります。
2. 現役並み所得者(3割負担)の判定はどのようにするのですか?
一部負担割合の判定は前年中の所得等により世帯単位で行います。同一世帯に市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる場合は、その世帯に属する被保険者全員が3割負担になります。
ただし、市町村民税課税所得が145万円以上の方がいる場合でも、以下のいずれかに該当する場合は2割負担(または1割負担)となります。
① 同一世帯の被保険者が1人で、被保険者本人の年収が383万円未満の場合。
② 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の収入の合計額が520万円未満の場合。
③ 同一世帯の被保険者が1人で、かつ同一世帯に70歳~74歳の方がいる場合で、被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計額が520万円未満の場合。
④ 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、同一世帯の被保険者の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合。
3. 2割負担となる方の判定はどのようにするのですか?
一部負担割合の判定は前年中の所得等により世帯単位で行います。同一世帯に市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる場合で、以下のいずれかに該当する場合は、その世帯に属する被保険者全員が2割負担になります。(現役並み所得者(3割負担)の方は除きます)
① 同一世帯の被保険者が1人で、被保険者本人の「年金収入(※1)+その他の合計所得金額(※2)」が200万円以上の場合。
② 同一世帯の被保険者が2人以上で、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上の場合。
※1 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2 「その他の合計所得金額」とは、年金収入以外の事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
4. 所得が少ないのですが、入院するときに病院に支払う医療費負担が少なくなりますか?
世帯全員の市町村民税が非課税の被保険者の方は、医療機関でオンライン資格確認を受けるか資格確認書(任意記載事項あり)を提示することで、窓口で支払う自己負担限度額(月額)及び入院時の食事代の負担が軽減されます。
保険料について
1. 保険料の通知はいつ届きますか?
保険料の通知は毎年7月末までにお送りします。年度途中に資格取得された方には、資格取得した月の翌々月にお送りします。
2. 他の市町村に転居したとき、保険料額は変わるのですか?
富山県内の他の市町村に転居した場合、保険料は同一の基準で計算されますので1年間の保険料額は変わりませんが、保険料の納付は市町村ごとに行いますので、市町村ごとの納付額を月割で按分計算し精算を行います。
富山県外に転居した場合、転出月以降の保険料は転出先で新たに決定されます(富山県分は精算処理を行います)。保険料率は都道府県ごとに異なるため、1年間の保険料額は変わります。
3. 保険料率の見直しはどのようにしていますか?
保険料率(均等割額と所得割率)は県内で統一されており、安定した財政運営を確保するため、2年単位で後期高齢者医療の費用と収入額を見込んだ上で決められます。
4. 年度途中で75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者になった場合の保険料はどうなるのですか?
当該年度の保険料については、月割計算(75歳の誕生月以降分)した保険料を納めていただきます。75歳の誕生月は、それまで加入していた健康保険の保険料計算の対象外となります。
保険料の支払いについて
1. 「督促状」や「催告書」が届いたのですが?
納付書により保険料を納めていただく必要がある方が、何らかの事情で納期限までに納められていない場合に、お住まいの市町村から「督促状」や「催告書」が送付されます。
「督促状」や「催告書」が届いた場合は、これまでに保険料の納め忘れ等があります。お早めに保険料を納めてください。ご不明な点は、発送元の市町村へお問い合わせください。 なお、保険料の支払いが困難な場合は、お早めにお住まいの市町村窓口にご相談ください。
※保険料は全ての方が年金から天引きになっているわけではありません。納付書が届いていないかご確認ください。
※保険料額の変更等により、年金天引きから金融機関窓口での納付に切り替わる場合があります。ご注意ください。
2. 保険料を滞納した場合はどうなりますか?
災害などの特別な事情もなく保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることがあります。
○財産の差押え・・・
保険料の納付が可能であるにもかかわらず滞納している方は、財産(預金や不動産等)の差押えを受ける場合があります。
○短期被保険者証の交付・・・
通常の被保険者証よりも有効期限が短い被保険者証を交付します。
○保険給付の制限・・・
特別な事情もなく、一定期間以上滞納している方は、療養費・高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止めることになります。
3. 保険料を納めると、税金が安くなるのですか?
納付された保険料は全額、所得税・住民税の控除の対象(社会保険料控除)とすることができます。
公的年金等からの天引き(特別徴収)で納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除とすることができ、納付書や口座振替(普通徴収)により納付された場合は、実際に納付した方の社会保険料控除とすることができます。
第三者行為について
1. 交通事故や傷害事件など第三者の行為によってケガをしたとき、後期高齢者医療被保険者証を使って受診できますか?
後期高齢者医療被保険者証を提示し、保険医療機関で治療を受けることは可能です。
ただし、仕事上のケガ(労災保険の適用)や故意によるケガの場合、後期高齢者医療は使えないことがあります。
なお、後期高齢者医療被保険者証を提示して治療を受ける場合、市町村の後期高齢者医療担当窓口に必ず「第三者行為」に関する届出が必要です。
●市町村の後期高齢者医療担当窓口へ届出に必要な書類等
・後期高齢者医療被保険者証 ・印鑑 ・交通事故証明書
2. 第三者の行為によってケガをした治療費の請求先はどうなるのですか?
後期高齢者医療を使って治療を受けた場合、後期高齢者医療広域連合は治療に要した費用のうち一部負担金を除いた額を保険医療機関に対し給付(支払)を行います。
しかし、給付の事由が第三者の行為によって生じた場合、後期高齢者医療広域連合は第三者の代わりに一時的に立替をしていることになるため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第1項に基づき損害賠償請求権を取得し、第三者に対し保険医療機関に支払った額を限度に請求することになります。
なお、この請求事務は専門的な知識を必要とするため、高齢者の医療の確保に関する法律第58条第3項に基づき、後期高齢者医療広域連合から国民健康保険団体連合会に委任することができることとされています。
3. 相手方と示談するとき、事前に連絡は必要ですか?
不用意に示談をしてしまうと、第三者に対する治療費の損害賠償請求が被害者本人・後期高齢者医療広域連合ともにできなくなる可能性があります。
治療が終了する際には後遺症の可能性など慎重に確認のうえ、相手方と示談する際には、必ず後期高齢者医療広域連合担当窓口へ相談をお願いします。
4. 交通事故や傷害事件のほかに「第三者行為」に該当するものはありますか?
他人の飼い犬やペットにかまれた場合も第三者行為の対象になります。その他にも、自転車による事故や建物・施設における設備欠陥による事故などが対象になる可能性があります。